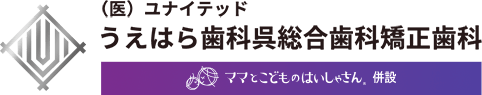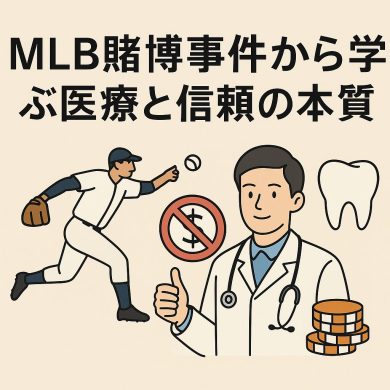不正の代償と誠実の力──MLB賭博事件から学ぶ医療と信頼の本質
みなさんこんにちは!お口の健康から全身の健康を創造する医療法人ユナイテッド理事長上原亮です。
まず、今回の事件のあらましから整理します。
米国時間11月9日、米東部地区連邦検察庁は、Cleveland Guardiansの投手、Emmanuel Clase(27)選手と Luis Ortiz(26)選手を、スポーツ賭博およびマネーロンダリング共謀の罪で起訴したと発表しました。 AP News+2SI+2
起訴状によると、両選手は試合中の“特定の球種・球速を意図的に投げる/あるいは打席の初球でボールとなるような投球を行う”という操作に関与し、それを賭博師と連携して「プロップベット(個別の賭け)」の対象とした、とされています。 SI+1
たとえば、Clase投手は2023年5月ごろから、賭博者と連絡をとり、あらかじめ「この球をボールにする」という合意をしており、その情報をもとにオンライン賭博サイトで数千ドル単位の賭けが行われたとのこと。賭博師側は少なくとも40万ドル(約6 100万円)以上の不正利益を得たと報じられています。 ABC News+1
また、Ortiz投手は2025年6月15日および6月27日の2試合で、あらかじめ特定の投球を“ボール”にする約束を賭博師と交わし、見返りに5 000ドル、7 000ドルをそれぞれ受け取ったとされています。 ガーディアン+1
このような事案が明らかになると、スポーツそのもの、公正な競争、ファンの信頼というものが深く揺らぎます。リーグ側も「ファンがフェアプレーを前提に応援/観戦するという信頼を裏切るものだ」と強く表明しています。 MLB.com
日本における野球賭博問題
日本でも、プロ野球やアマチュア野球をめぐって「賭博・八百長」問題は過去に何度も取り沙汰されてきました。例えば賭博に関与した選手・関係者に対して永久追放や厳罰が科された事例もあります。これには、次のような背景があります:
野球というスポーツが社会的影響力を持ち、「子どもたちの憧れ」「地域のシンボル」とされる面が強い。
選手・監督・審判・運営の信頼性がそのまま「競技の価値」「観る価値」につながる。
八百長・賭博が公になると、ファン離れ・スポンサー離れ・報道の信頼喪失を招きかねない。
日本のプロ野球・アマチュア野球では「賭博禁止」「八百長禁止」のルールが極めて厳格で、違反した場合の処分もまた重い。
このように、スポーツの世界における「賭博×不正」は、競技場を出て社会全体のモラル・信頼感にまで影響を及ぼす重大なテーマです。
なぜ「永久追放」が出るのか?
賭博や八百長に関わった選手が「永久追放」となるのは、以下の理由が主です。
信頼回復がほぼ不可能:ファンや社会が選手・チームを信頼できなければ、観戦・応援という文化自体が破壊しかねない。
再発防止の強いメッセージ:永久追放=「二度とグラウンドに立てない」という制度的抑止力。
スポーツ産業としての保全:放置すればスポンサー・メディア・地域との関係が損なわれる。
道徳的・教育的責任:子どもたちが見る世界で「不正して勝つ」というメッセージを許してはならない。
したがって、日本の野球界では「賭博・八百長」と一線を画すという文化・制度が定着しています。
医療の世界と「信頼」との共通点
では、なぜこのような「信頼」がスポーツだけでなく医療・歯科にも不可欠なのか。あなたのクリニックである「うえはら歯科」での日々の診療とも重ねて考えましょう。
信頼・誠実さこそが価値
スポーツ選手が「勝利」だけでなく「正しく・公正に勝つ」ことを求められるように、医療機関も「結果(歯が良くなる/機能回復する)」だけでなく、「プロセス(説明・同意・診療の透明性)」が問われます。
患者さんは「この先生・この医院なら信頼できる」と感じて通います。いったんその信頼が壊れれば、回復は極めて困難です。
あなたのように「インプラント」「小児矯正」「訪問診療システム」など、高度かつ多岐にわたるサービスを提供している医療法人では、特にスタッフ・患者・地域からの信頼がクリニックのブランド・成長に直結します。
誠実な説明と妥当な技術選択
医療において「不正」は例えば、必要以上の処置を行う、過剰な料金設定をする、説明を省略するなどの形で現れ得ます。これはスポーツの賭博不正と同じく「隠れたインセンティブ」が働くケースです。
患者さんが「なぜこの治療が必要か」「リスク/代替手段は何か」「料金・アフターケアはどうか」を理解できなければ、結果として“信頼の後退”を招きます。
また、技術的にも誠実であること。たとえば、最新のデジタル設備を導入しながらも、コスト・リスク・患者さんにとっての利益を丁寧に伝える。これは、クリニック経営にも、患者満足にもプラスです。
「うえはら歯科」のポジション — 信頼を創る3つの柱
あなたが理事長として先導されている「うえはら歯科」には、信頼構築を支える明確な柱があります。これをあらためて読み直し、ブログ読者にも「なぜ当院を選んで頂けるか」を伝えましょう。
柱①:丁寧なコミュニケーション
初診・相談段階から「口腔内だけでなく全身の健康」という視点を掲げ、患者さんのお話にじっくり耳を傾ける。
治療内容・選択肢・メリット・デメリットをしっかりご説明。例えばインプラントなら「骨量・隣接歯・全身疾患」「メンテナンス期間」等。
小児矯正・訪問診療など、ライフステージやご家庭の状況を踏まえたプラン提示。
柱②:誠実な技術・設備選択
デジタル化(CT、IOSスキャナー、In-house CAD/CAM)などハイレベルな設備を導入しつつ、投資の背景・費用対効果をスタッフ・患者さんに透明にする。
衛生士多数配置・SPT(メンテナンス)体制・訪問診療システムという継続的ケアの仕組みを確立し、「治療して終わり」ではなく「健康維持まで」を視野に入れる。
スタッフ教育・長期勤続を重視し、技術・接遇の質を高く保つこと。スポーツチームと同様“信頼できるチーム”作り。
柱③:地域・患者との信頼関係
地域に根づくクリニックとして、透明な料金告知・誠実な対応・アフターケアも怠らない。
患者さん一人ひとりにとって「この医院なら安心」「紹介したい」という存在であること。スポーツでいえば「常勝チーム」ではなく「信頼されるチーム」。
ブログ・SNS発信を通じて「お口の健康から全身の健康を創造する」というミッションを共有し、患者さん・地域を巻き込んだ健康啓発を行う。
なぜ、不正は「信頼」を壊すのか
さて、今回のスポーツ賭博事件に戻ると、なぜこれほどまでに「許されない」とされるのでしょうか。それを医療現場ともリンクして考えます。
不正は「勝つ/得をする」「利益を得る」といった短期的インセンティブに引きずられて起きます。今回の投手のケースでは「賭け師との約束」「賄賂・キックバック」という明らかな利益動機があったと起訴状にあります。 SI+1
その結果、ファン・観客が「この試合は公平ではないかもしれない」「選手が真っ正直にプレーしていないかもしれない」と疑念を持ってしまいます。これはスポーツの価値そのものを損なう行為です。
医療でも、もし「結果を出すために本来不要な処置をする」「説明を省略して収益を優先する」などがあれば、患者さんの信頼を根底から崩してしまいます。
信頼が壊れると、どんなに技術が高くても、どんなに設備が整っていても、患者さんは紹介しなくなります。口コミ・評判・リピートは信頼の上に成り立っています。
逆に、不正を未然に防ぎ、透明性・誠実性・継続的な改善を掲げている組織は、長期的に強く・存続性の高い組織となります。
結びに:丁寧・正直な診療を通じて
今回の米大リーグの事件、そして日本における賭博・八百長問題を改めて見つめると、“小さな不正・省略・安易な利益優先”が信頼という大きな資産を破壊するという教訓が浮かび上がります。
あなたが率いる「うえはら歯科」も、まさに「信頼という資産」を日々積み重ねておられると感じます。以下をスローガンとして、ブログ読者・患者さんに向けてメッセージを届けましょう。
「お口の健康から、全身の健康を創る。丁寧・正直な診療で、信頼という土台を築き続けます。」
患者さん一人ひとりと真摯に向き合い、説明・同意を丁寧に行う。
高度技術を導入しながらも、「本当に必要か」「患者さんにとっての価値か」を考え抜く。
信頼関係を育むスタッフ体制・ケア体制を整え、「紹介されるクリニック」「地域に愛されるクリニック」を目指す。

「SPT(歯周病のメインテナンス)」→ [歯周病ページへの内部リンク]
「お口の健康から全身の健康へ」→ [訪問診療ページへの内部リンク]
「スタッフと共に歩む」→ [求人ページへの内部リンク]
また当院は「ママとこどもの歯医者さん」グループに加盟しています。
ままとこどものはいしゃさん YouTube
うえはら歯科ではWEB予約を承っております
下記をクリック↓
うえはら歯科WEB予約
またうえはら歯科では予防医療をお手伝いしてくれる歯科衛生士を募集しております。現在8名の衛生士が在籍しております。
衛生士の仕事を探しておられる既卒の衛生士さん、今衛生士学校の学生で将来衛生士になられる学生さん
まずは見学からいかがですか?
うえはら歯科就職サイト
きょうもご覧いただきありがとうございました!